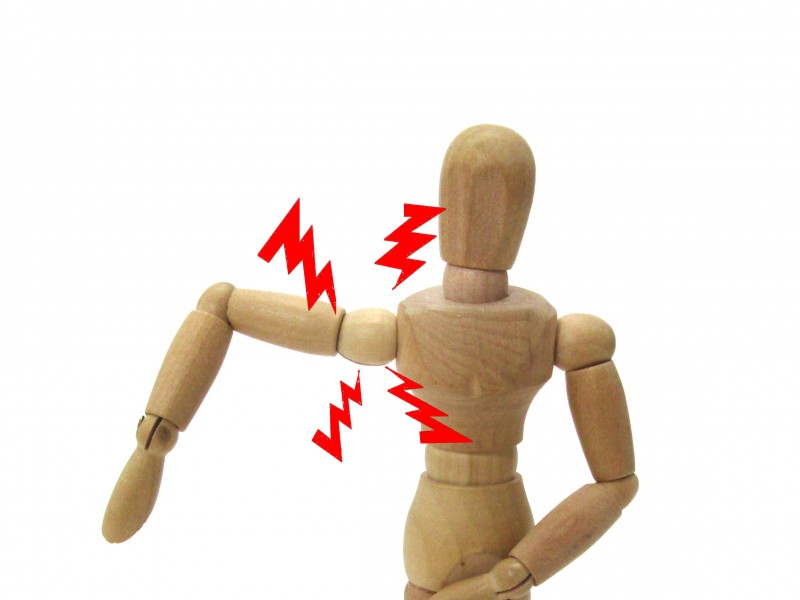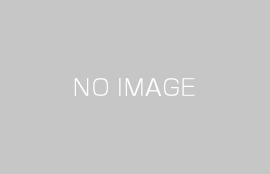腕を上げようとしたときに、肩の奥で「ズキッ!」と激しい痛みが走る。
または90度以上あげられない・・・
これは**インピンジメント症候群(肩の挟み込み症候群)**の典型的な症状です。
「単なる使いすぎだろう」と放置しがちですが
この症状の裏には、日々の姿勢の悪さ(猫背)や組織の慢性的な炎症といった、根本的な原因が隠れています。
城ヶ崎さくら並木の鍼灸院では、このインピンジメント症候群に対し、痛みの原因を根本からリセットする鍼灸アプローチを提供しています。
1. 肩の「挟み込み」はなぜ起きる?主要な2つの原因
インピンジメント症候群は、肩の天井部分にある肩峰(けんぽう)と、腕の骨(上腕骨頭)の間で、腱や袋(滑液包)が挟まれることで起こります。その原因は大きく2つに分けられます。
【最も厄介な実行犯】機能的・運動学的要因(姿勢の異常)
挟み込みが起こる原因の約8割は
**肩や背中の「動き方」**に問題があると考えられています。
| 悪い習慣 | 肩で起きている問題 | 挟み込みのメカニズム |
| 猫背・巻き肩 | 肩の土台の不安定化 | 猫背になると、肩甲骨が正しい位置から前にズレて固定されます。その結果、腕を上げるときに、肩峰の下の隙間(トンネル)が異常に狭くなってしまいます。 |
| インナーマッスルの機能低下 | 骨頭の位置のズレ | 肩の安定を担う小さな筋肉(腱板)が、疲労や血行不良でうまく働かなくなると、腕の骨(上腕骨頭)が上に引き上げられ、狭くなったトンネルの天井(肩峰)に激しく衝突してしまいます。 |
つまり、猫背や肩の位置異常という「実行犯」がいるせいで、肩の組織が常に間違った軌道で動かされ、挟み込みが起こってしまうのです。
【慢性期の敵】構造的要因(肩峰下滑液包の肥厚・炎症)
当院のような慢性期の症状を扱う鍼灸専門院で特に多く見られるのが
この肩峰下滑液包(けんぽうかかつえきほう)の肥厚や炎症です。
滑液包とは、骨と腱の摩擦を防ぐクッション材の役割を果たしています。
-
慢性的な負担の蓄積: 猫背や繰り返しの無理な動作により、滑液包が長期的に圧迫・摩擦を受け続けると、自己防衛反応として滑液包そのものが分厚く(肥厚)なります。
-
物理的な狭窄: 分厚くなった滑液包は、それ自体が**「かさばる異物」**となり、ただでさえ狭い肩峰下腔の隙間をさらに埋め、物理的に腱が挟まれる原因となります。
鍼灸治療では、この慢性的な炎症で硬くなった滑液包や周辺組織の血行を改善し、炎症による痛みを鎮めるアプローチを得意としています。
2. なぜ「複数回の施術」が必要なのか?
この症状でよく聞くのは「1回で・局所コースで治したい」という内容です。
しかしインピンジメント症候群の慢性的な原因を考えると、残念ながら1回の施術で完治することは極めて難しいと言わざるを得ません。
原因は「状態の悪さ」ではなく「長年の習慣」
インピンジメント症候群の真の原因は、上記で解説した通り
長年の「猫背」や「肩の位置異常」という悪い習慣が体に染みついたこと
にあります。
これは、肩に「一時的にかかる負担」ではなく
何年もかけて少しずつ組織を痛めつけてきた慢性的な負担状態です。
回数が必要な理由
-
積年の緊張の解除: 鍼灸でまず痛みを鎮め、深部に固着した**猫背の原因筋(大胸筋、肩甲挙筋など)**の緊張を解きほぐすのに時間がかかります。
-
動きの再教育: 緊張が取れた後、正しい肩甲骨の動き(肩甲上腕リズム)を体に覚え込ませるための運動療法やリハビリが必要です。これは脳と体の再学習であり、必ず複数回の反復が必要です。
-
炎症の鎮静と吸収: 肥厚した滑液包の炎症を完全に鎮静化させ、組織の柔軟性を回復させるためには、継続的な血流改善アプローチが必要です。
当院では、患者様一人ひとりの「悪い習慣の深さ」と「組織の損傷度」を正確に評価し
段階的な治療プラン(通常は5~10回以上)を立てて、根本改善を目指します。
肩の痛みを「歳のせい」と諦めず、根本原因である姿勢の改善と組織の機能回復を、私たちと一緒に目指しましょう。
城ヶ崎さくら並木の鍼灸院
-
電話番号: 0557-51-3663
-
インターネット予約: [インピンジメント症候群専門治療のご予約はこちら] (https://kenkounihari.seirin.jp/clinic/1195/reserve)
-
駐車場: 完備しております。
-
関連治療: 五十肩、慢性肩こり、姿勢矯正