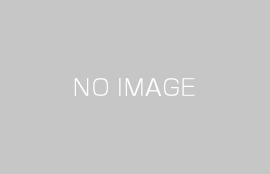「頻繁にトイレに行きたくなる」
「排尿時にツーンとした痛みがある」
このようなつらい症状は、多くの女性が悩む膀胱炎かもしれません。
膀胱炎の治療といえば、一般的に「抗生物質」が思い浮かびますが
実は菌が検出されない「無菌性膀胱炎」も存在します。
この無菌性のつらい症状には、薬では届かない鍼灸治療が非常に有効であることをご存知でしょうか?
今回は、膀胱炎のタイプと、鍼灸がなぜこの症状の根本改善に役立つのかを、東洋医学の視点から詳しく解説します。
膀胱炎の種類:「有菌性」と「無菌性」の違い
膀胱炎は、その原因によって大きく二つに分けられます。
1. 有菌性膀胱炎(細菌性)
尿検査で細菌(菌)が検出される一般的な膀胱炎です。主な原因は大腸菌などの細菌感染で、通常は抗生物質の服用で比較的早く改善が見込めます。
2. 無菌性膀胱炎(非細菌性)
頻尿や残尿感、膀胱の不快感などの症状があるにもかかわらず、尿検査で細菌が検出されないタイプです。
この場合、抗生物質を服用しても菌がいないため、効果がないことがほとんどです。
この無菌性のつらい症状は、実は膀胱壁の血流障害や冷えなどが原因で起こっていることが多く、鍼灸治療が非常に適応となります。
無菌性膀胱炎のメカニズム:鍼灸が効く理由
無菌性膀胱炎の症状は、自律神経の乱れや冷えが引き金となって起こると考えられます。そのメカニズムを見ていきましょう。
- 冷えや疲労が引き金に: 慢性的な冷えや過度な疲労・ストレスにより、膀胱周りの血流が障害されます。
- 膀胱壁の機能低下: 血流障害が起こると、膀胱を構成する平滑筋の伸びる力(伸張性)が低下したり、膀胱の粘膜が過敏になったりします。
- つらい頻尿の発生: その結果、膀胱に尿が少し溜まっただけでも「満タンだ」と脳が勘違いし、頻繁に尿意を感じる(頻尿)ようになります。
痛みのメカニズムと鍼灸による根本アプローチ
さらに、膀胱炎の排尿時の痛みは、神経の興奮によって引き起こされます。
- 膀胱壁の異常な反応は、主に排尿に関わる**骨盤神経(S2〜S4)**に異常な興奮を生じさせます。
- この興奮が一定のレベルを超えると、痛みを感じる**陰部神経(S2〜S4/体性神経性)**も連動して興奮し、ツーンとした排尿痛として現れます。
鍼灸治療は、この興奮している骨盤神経や陰部神経の働きを鎮め、血流を改善することで、膀胱の機能を正常に戻すことを目指します。
当院が行う鍼灸による治療法
当院では、膀胱炎の症状に特化し、骨盤内の神経と血流に直接働きかける施術を行います。
1. 神経を鎮める特効ツボへのアプローチ
興奮した骨盤神経や陰部神経にアプローチするため、以下のツボに鍼を行います。
- 八髎穴(はちりょうけつ):仙骨(お尻の割れ目の上にある骨)にあるツボ群。骨盤内の血流を改善し、骨盤神経の働きを整える特効穴です。
- 中極穴(ちゅうきょくけつ)〜曲骨穴(きょくこつけつ):下腹部にあるツボ。膀胱の反応が最も強く現れる部位であり、直接的に膀胱の緊張を緩める目的で刺激します。
- 大赫穴(だいかくけつ):下腹部にあるツボで、特に泌尿器系の不調に効果的です。
2. 徹底的に行う温熱療法
膀胱炎の改善には、冷えを取り除き、血流を促す温熱療法が非常に有効です。
しかし、市販のお灸(せんねん灸のような小さな火力)では、膀胱の奥深い冷えを取るには刺激が物足りないと感じる方が多いです。
当院では、鍼と同時に**しっかり刺激(ほんの小さな灸痕が残る)の電気のお灸(N灸)**を用いて、骨盤内を深部から温め、血流障害を強力に改善します。
この温熱刺激が、膀胱平滑筋の伸張性を回復させ、頻尿の改善につながります。
同時に赤外線ライトやホットパック、箱灸も活用して徹底的に温めます。
最後に
抗生物質が効かない無菌性膀胱炎は、慢性化しやすく、生活の質(QOL)を大きく低下させます。
「冷え」や「ストレス」といった根本原因に働きかける鍼灸治療は、薬に頼らず、身体の内側から膀胱の機能を正常に戻すことを目指します。
つらい頻尿や残尿感でお悩みの方は、ぜひ一度、当院にご相談ください。